|
人生を劇変させる内省とは? 「内省」の凄い効果 このページでは、すべての人の人生に必須のテクニック「内省」(リフレクション) の絶大な効果について、実際の体験談を交えながら、詳しく解説していきます。 |
「内省」を強制的にできる仕組みを導入した新コーチング・プログラムの詳細はこちらのページをご覧ください。
|
プログラムで内省を行ったメンバーの感想 |
内省のメリットなどの解説の前に、まずは最近私(中西)の元に届いた「内省」を実践した皆さんからの感想をご覧ください。

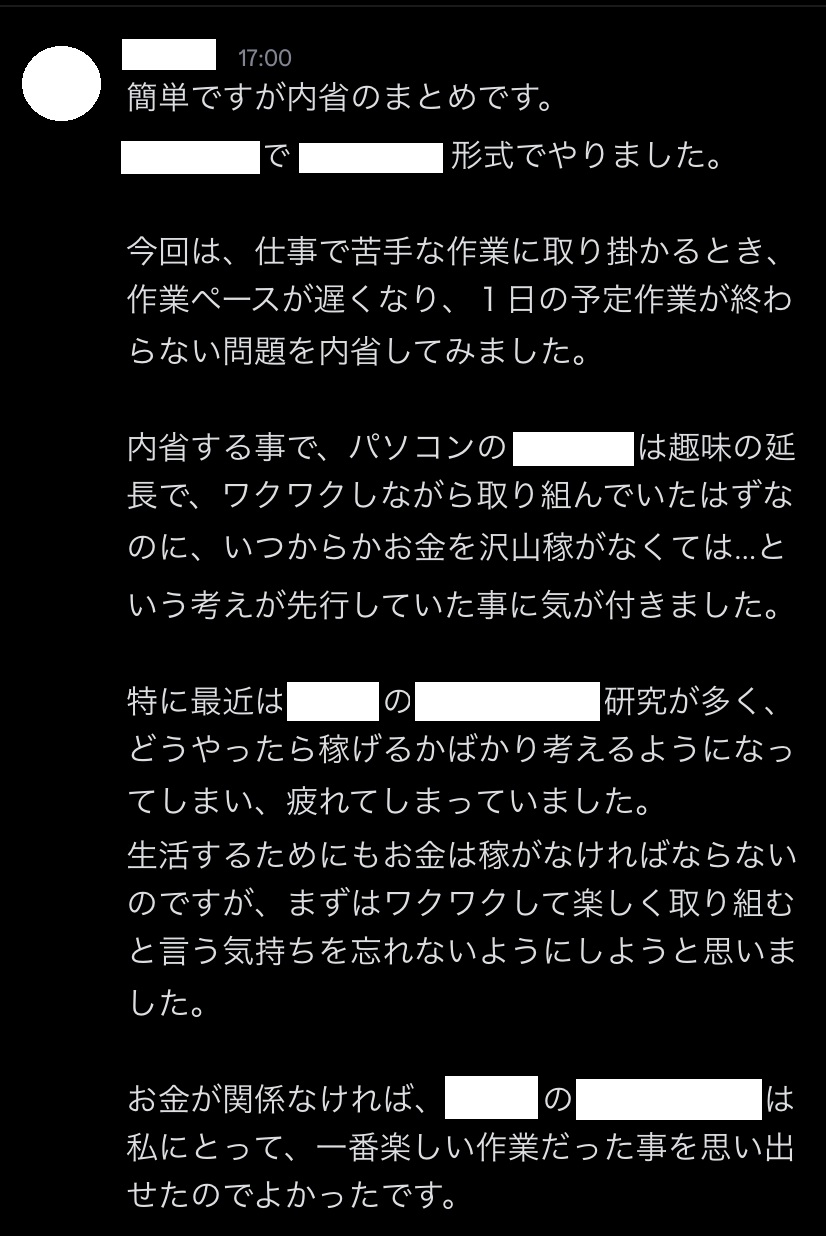
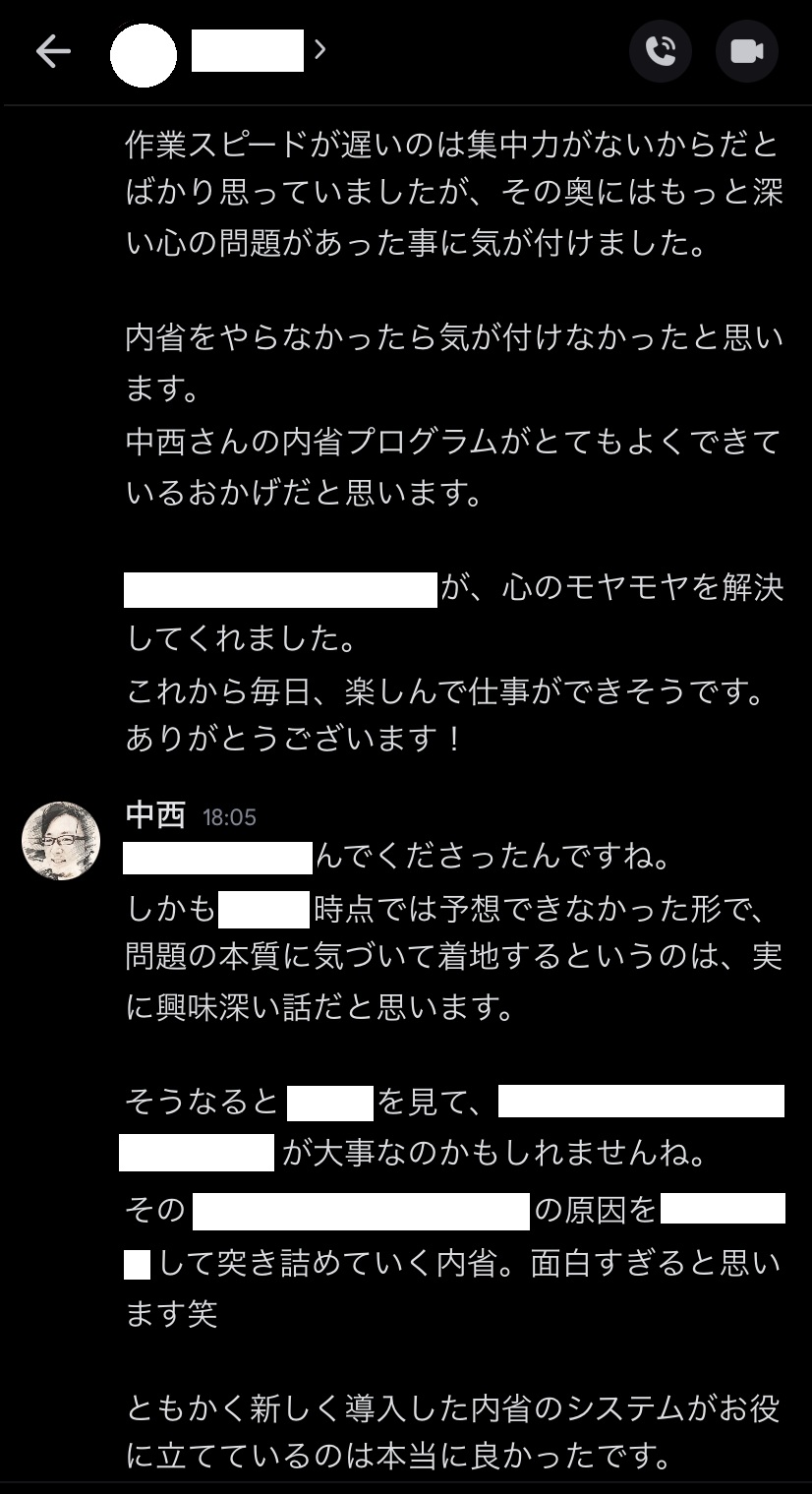
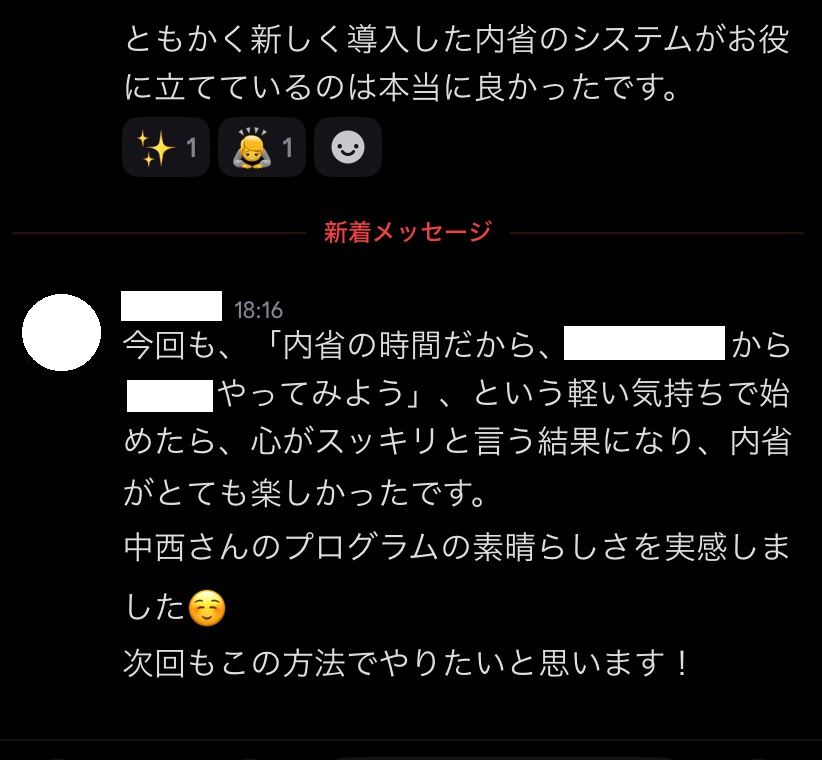
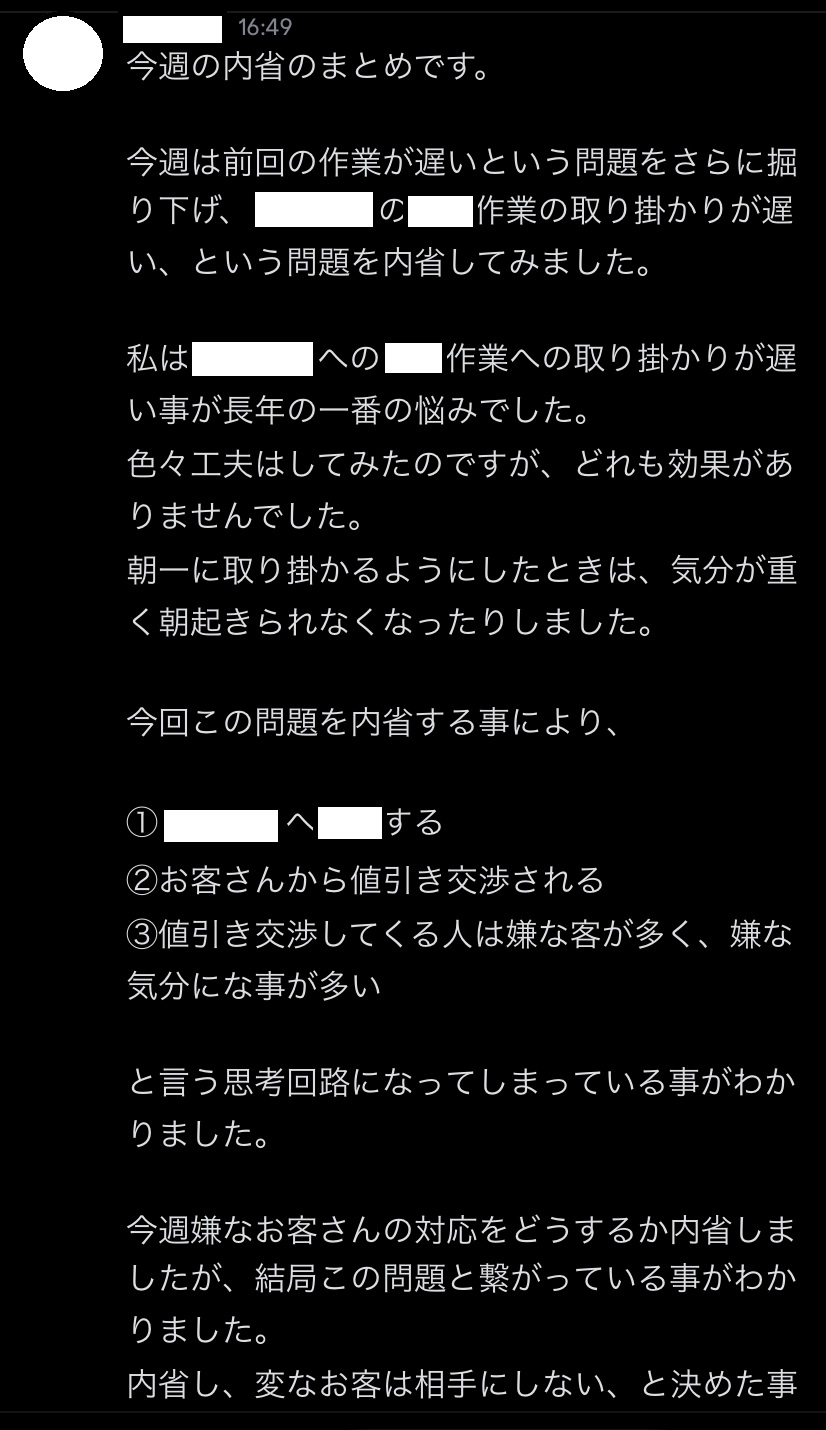
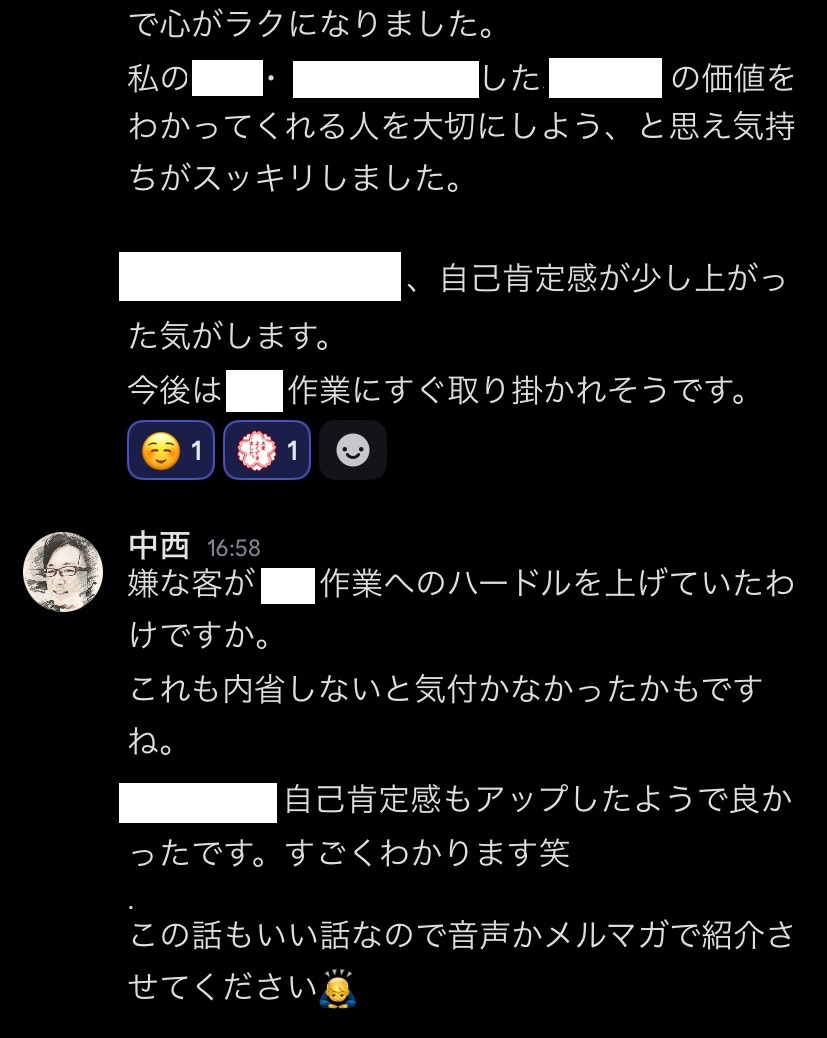
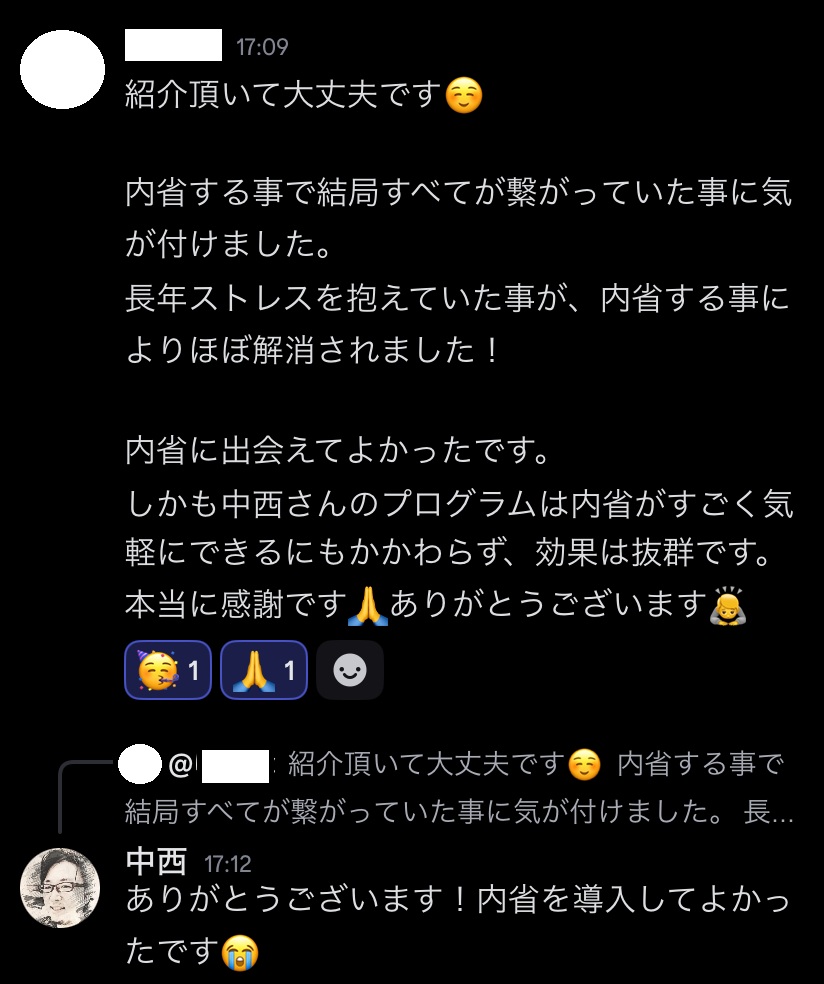
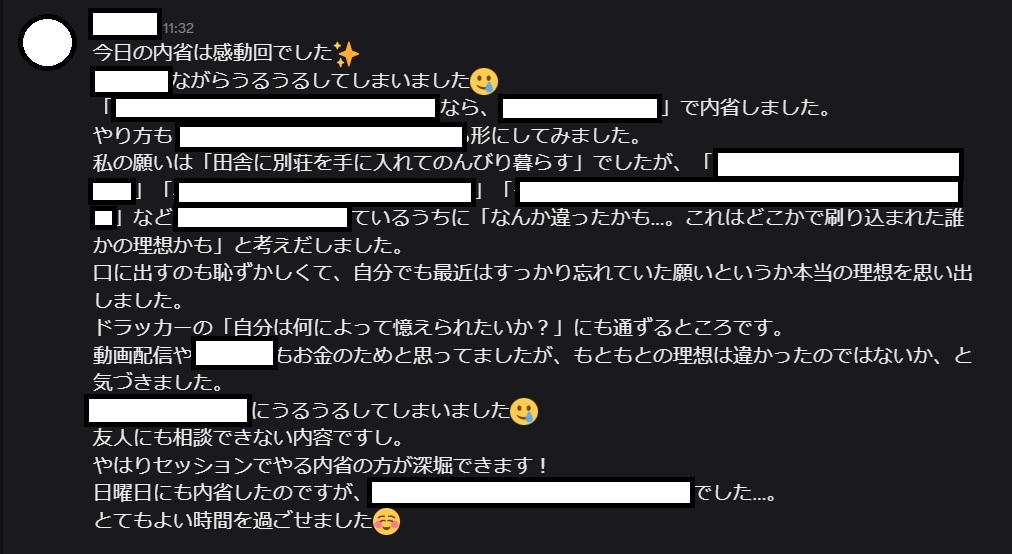
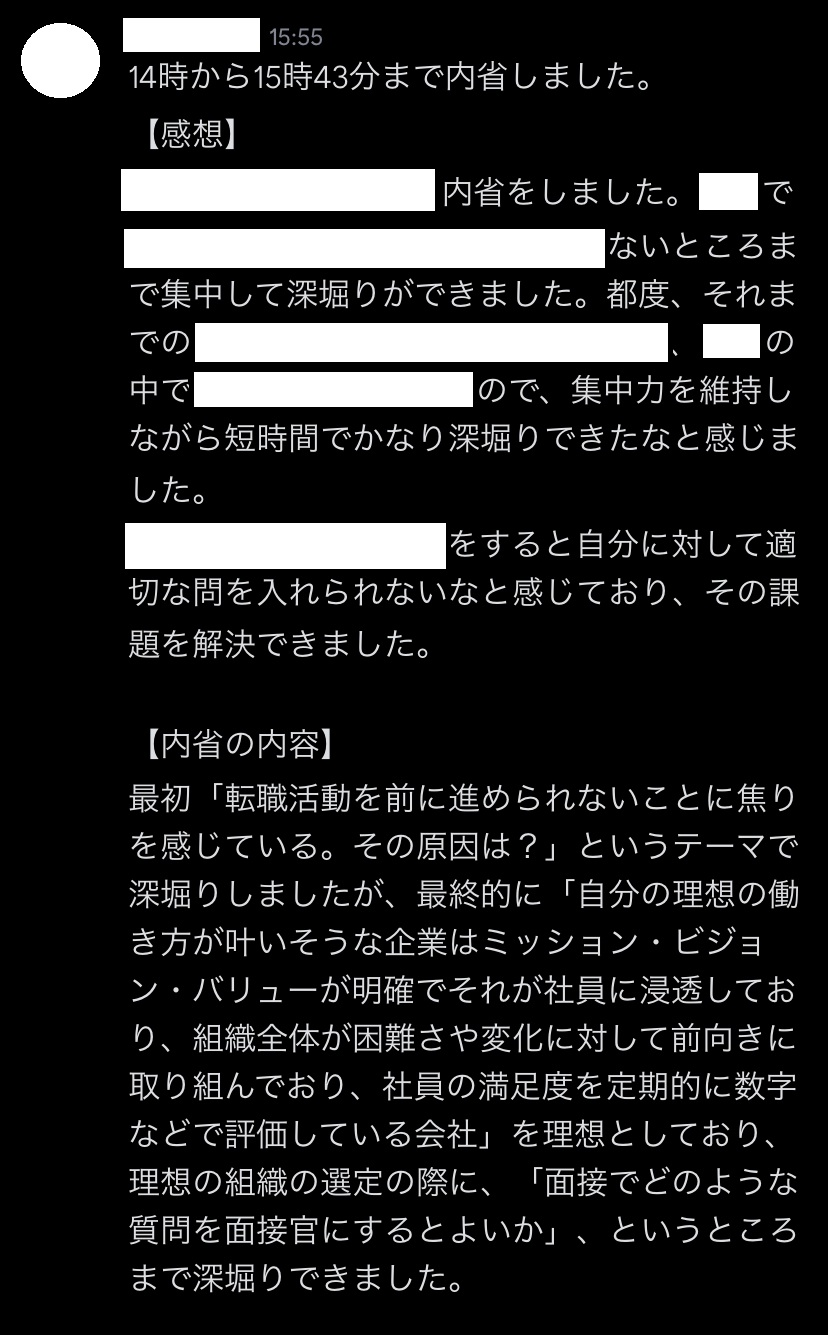
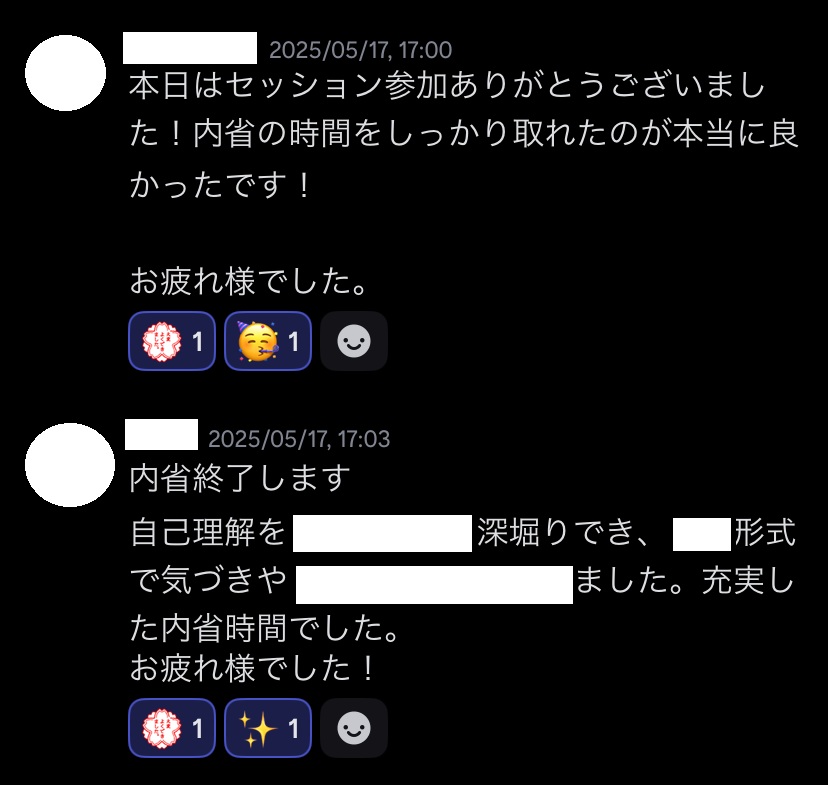
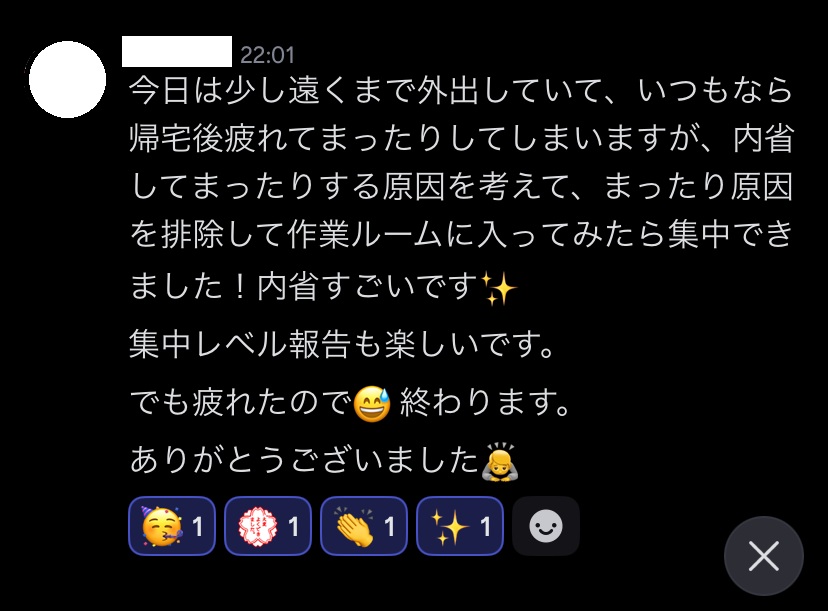
※以上は私の元に届いた感想のごく一部です。他にも多数いただいてますが、私の独自の内省法のネタばれになる感想が多く、掲載が難しかったので泣く泣くカット笑
上記の感想でも実践した皆さんが感じている効果は、ある程度伝わるかと思います。
では、以下より本題へ。
|
内省の11個のヤバいメリット(体験談) |
こんにちは、中西です。
誰もがそうですが、日々のルーティーンとしての運動、勉強、掃除、たまにやる部屋の断捨離、年に何回か行く歯医者さんの定期健診など、
“緊急でないけど重要”
なタスクを常に抱えています。
しかし、多くの人はそれをなかなか実行できない悩みも同時に抱えています。
理由は重要なタスクではあるけど、緊急性がないから。この「緊急ではないけど重要」なタスクのことを「第二領域」と言います。
(第二領域は世界的ベストセラー「7つの習慣」で提唱された概念。「緊急かつ重要」な第一領域~「緊急でも重要でもない」第四領域まである)
緊急性が高いタスクなら、多くの人は締め切り効果で実行しやすいのです。ましてお仕事関連で締め切りが明確にあるタスクなら、強制力が高いので、通常は誰でも実行できます。
しかしこの第二領域のタスクについては、仕事でもプライベートでも、緊急性がないので、なかなか実行しづらいのです。
この多くの人がなかなか実行できずに困っている(どころかそのせいで人生が大きく停滞している)
【 第二領域のタスク 】
を、半ば強制的に実行するためのコーチング・プログラムを作れないかと考えていたのが、2022年ごろでした。そこから試行錯誤を繰り返しまくり、
「第二領域コーチング」
のプログラムを2023年に作り上げリリースしました。
この第二領域のコーチング・プログラムは、今年で3期目になります。
私はこのプログラムの管理人&コーチとして、2期までの2年間で、累計3000回以上のコーチングをしてきました。(自分でも数えてみてビックリ!)
さらに、先月からスタートしたこの3期目からは、第二領域の典型ともいえる
「内省」(リフレクション)
をプログラムの中に組み込み、セッション中にメンバーの皆さんが強制的に内省を実行できる仕組みにしました。
内省とは、一般的には
「自分の言動・経験・感情・考え・価値観などを深く省みること」
といった意味合いです。といっても、解釈は幅広いので、ざっくりと
「人生に重要な様々なテーマについて、深堀りして考えること」
ぐらいの解釈で、大筋間違いないかと思います。
この内省が不要な人は存在しません。どんな仕事をしていても、学生さんでも社会人でも、誰にとっても必要なことなのです。
この内省(リフレクション)は、経済産業省も「人生100年時代の社会人基礎力」として内省を位置づけて認めています。それほど重要なスキルなのです。
-www.meti_.go_.jp_.jpg) 出典:経産省
出典:経産省
なぜ、この内省が重要なのか?
それは日々目の前のタスクに没頭しているだけだと、様々な課題・問題が発生していても、そのこと自体に気づかなかったり、気づいても原因がすぐにはわからないことが少なくないからです。
現代人は本業で非常に忙しい一方で、隙間時間は動画やSNSなどでネットを閲覧したり、LINEで誰かとコミュニケーションを取ったり、インプットをしたりして時間を埋め尽くします。
休日は休日で予定を入れたり、リラックスした時間を過ごします。
この繰り返しが続くと、自分自身の事について改めて時間をとり、根本的に振り返る時間が持てなくなります。
実際、内省の時間は後回しにされがちで、プライベートの時間でわざわざそんなことをするぐらいなら、何か遊ぶか勉強するか、漫画やゲームやネットを見ていたほうがマシ、と言うことになりやすいのです。
惰性でなんとなく流されるまま日々を過ごさないようにするためには、どこかのタイミングで(できるだけ一定の頻度で)しっかりと、自分自身の内面や状況、行動、考え方などを振り返る必要があります。
ただし、単に振り返るだけでなく、自分の価値観や最近の気づきや体験・感じていることなどを踏まえて、たとえば
「本当にこのままでいいのか?」「何が問題なのか?」「この違和感の正体は何だろう?」「なぜこの数日は調子がいいんだ?」「人間関係がこじれた本当の原因は?」「今の自分には何が足りない?」「本当は何をしたいのか?」「できない本当の原因は?」
といったことを、一定のタイミングで時間を取り、深掘りして自分自身に問いかける作業が必要になります。
この作業を「内省」と言います。
「リフレクション」
という言葉もあって似ていますが、リフレクションは、ある行動や経験について「何が起きて、どうすればよかったか」といったことを考える
改善的な振り返り
で、行動を見直して次に活かしていくイメージに近いです。
内省は、もう少し深掘りする感じで
「なぜ自分はそれをしたのか」「どう感じたか」「何を大切にしているのか」「今後どうしたいか」
といった価値観や考え・方針・ビジョンなども含めて考えるイメージです。
自分の内面や価値観に目を向ける行為で、自分のあり方や考え方を深く見つめていく作業になります。
そして、内省にはリフレクションも含まれていますので、リフレクションよりも内省の方が、より広義で深い意味合いになります。
内省 = リフレクション + 経験や感情の観察・価値観の問い・存在の振り返り・未来の考察etc
というようなイメージです。
(専門家によっては「内省≒リフレクション」という解釈をする人もいますが、私のプログラムでは「内省≧リフレクション」というリフレクションより内省がより広義のイメージで取り扱っています)
内省(リフレクション)によって得られるものをまとめると、こんな感じです。
|
内省(リフレクション)で得られるもの |
1. 自己理解の深化
自分の思考・感情・行動パターン、価値観、信念、強み・弱みが明確になる
自分らしい判断や生き方がしやすくなる
2. 感情の整理・コントロール
モヤモヤや不安の原因に気づき、適切に対処できる
心の平穏やストレス軽減につながる
3. 行動・習慣の改善
過去の行動を振り返り、うまくいったこと・改善点を把握できる
無意識のクセや習慣を見直すきっかけになる
4. 意思決定の質の向上
経験や価値観に基づいた、納得感のある判断ができるようになる
バイアスに気づき、合理的に選べる力が高まる
5. 学び・成長の促進
経験からの教訓や気づきを得て、次に活かせる
メタ認知が進み、より効率的な学習や成長が可能に
6. 目標達成のサポート
現状とのギャップに気づき、行動計画を調整できる
モチベーションを維持しやすくなる
7. 人間関係の改善
自分の言動が相手に与える影響を理解できる
コミュニケーションの質が高まり、共感力が育つ
8. 問題解決能力の向上
根本原因を冷静に分析し、効果的な解決策を導ける
多角的な視点で物事を考えられるようになる
9. 創造性・柔軟性の向上
経験や知識の再構成によって、新しいアイデアが生まれやすくなる
固定観念から抜け出し、自由な発想ができる
10. 自己肯定感・幸福感の向上
自分の努力や成長を実感することで、自信につながる
自分自身を受け入れられるようになり、満たされた感覚が育つ
11. 主体性の向上
自分の選択に責任を持ち、周囲に流されずに行動できるようになる
・・・・こんな感じなのですが、この内省を強制的にプログラム内で実行してもらう仕組みを先月から導入したところ、
私の予想をはるかに超えて、メンバーの皆さんから大好評をいただいてます。
まだ2ヵ月足らずですが、すでに内省によって人生が変わったという人も何人も出てきて、私自身が驚いております笑
また私が独自に考案した、ちょっと特殊な内省のやり方を皆さんに紹介したのですが、それもヤバいほど大好評。
(最大の理由は、皆さんの感想を聞く限り「楽しみながら内省が激しく進むから」かなと。
自分で言うのもなんですが、内省がゲーム的に面白くやれるようになるのです。このいわば”中西式内省”にハマりまくってる人も続出中。)
|
内省(リフレクション)の効果が凄すぎ(体験談) |
この内省(リフレクション)について、キャリアデザインを支援する株式会社マイキャリア代表の千葉裕子氏が、興味深い話をしていました。
内省(リフレクション)によって人生がどう変わるかが、具体的にわかりやすい内容だと思いましたので引用します。
|
リフレクション(内省)は人生を変えるインパクトがある。
例えば「研修が嫌いだ」という意見の持ち主は、それに紐づく実体験と感情によって研修に対するネガティブな価値観や信念が形成されているんだけど、「それって本当?」と前向きに疑うチャンスを与えてくれる。
振り返ってみると、たまたま一度つまらない研修を受けたとか、発表で緊張したなどの経験がトラウマになってるだけかもしれないし、
先輩等から「今日は研修?忙しいのに最悪やな」と言われただけで実際に最悪を体験していないのに、勝手に脳内でネガティブな印象が形成されているだけなのかもしれない。
一生引きずるんですか問題。私たちは、いつでも意見をアップデートすることができる。
おもしろくて役に立つ研修を受講したり、研修大好きな学び上手な人の話を聞いたりと新たな経験や意見に触れることでアンラーンが起こり、
記憶は上書きされ、次の瞬間から「学ぶことは価値ある楽しいことだ」という新しい価値観で世界を見ることができる。本当に人生が変わるのだ。
キャリアコンサルティングや職場における上司と部下の1on1の目的の1つがリフレクション。リフレクションの方法は学んでおいて損はない。 |
|
うまくいかないことがあると、ゼロリセットしたい気持ちになることってありますよね。
現実には時計の針は戻せないけど、だからといって考える意味がないわけではないと思います。
「もし経験前に戻れるなら、“自分は”何を変えるのか?」
を内省する行為がリフレクション。
経験から教訓や法則を見出し、気づきを次の行動に活かすために通らなければならない大事なプロセスですね。 |
・・・引用は以上ですが、他にもX上で様々な人たちが
「内省(リフレクション)で人生が変わった!」
という意見を大量に投稿しています。
参考になる体験談が多いので、以下にその一部を引用します。
内省(リフレクション)がどれほど効果があるのか、ピンと来ない方はぜひ読んでみてください。
(以下、すべて別々の人の意見です。25人分あります)
|
自分の考えや判断が「 正解 」であることの根拠を求めているだけの思考や壁打ち、内省(リフレクション)は、いくら深めても結果は浅い。
自己否定まではいかなくとも、自分の考えや判断を疑い自問自答することが自分を育てるって、マックで隣の席の女子高生が言ってた。 |
|
弊社の日報には反省の代わりにリフレクション(内省)という欄を設けています。
上手くいったことは?
などを書いていきます。例えばミスをしたときは、行動に注目するのではなくそこに至った考え方を振り返ります。
リフレクションによって事象を客観的に観察して改善していく能力が身につくと考えています。 |
|
今更ながらリフレクション(内省)の価値に気付いて驚いてる。習慣化できたら、日々の些細な出来事全てが学びになるじゃないか!
感情が振れた際に3回程度のなぜ?なぜ?なぜ?するだけで自分の価値観や癖がわかるように |
|
売上3000億マーケ企業に勤めてわかったこと。
リフレクション(内省)とは、自分や職場の出来事に対して自己理解を深めること。人材育成においては、自己成長を促し、失敗や課題から学べる。
コツは定期的に自己分析を行い、フィードバックを受けること。これだけでマインドが変わる。ぜひ試してみてね。 |
|
おはようございます まだ試行錯誤中ですが成果として充実した日々を送れている実感があります
上手くいかなかった事を反省ではなく学びと捉えて効果を出すには具体的にどうするか 今日もワクワクする1日になりそう |
|
当社では「リフレクション≒内省・振り返り」という言葉をよく使うんですが、この振り返りがものすごく重要だなと。それをしないと自分の中に何も学びが積みあがらない。
そして振り返るためには、本気の目標設定を全体重を乗せてしないと意味がないなと。改めて原点回帰。 |
|
内省、リフレクションしなきゃなぁと思う時は、何か小さいものでも心に残っている時。
でも何もない時でもリフレクションすると、気づいてなかった幸せに気づけたり、改善点を余裕を持って受け止められたりする |
|
エンジニアの成長には経験を単なる出来事で終わらせず、客観的・批判的に振り返り、次に活かすことが大切です。これを内省(リフレクション)と言います。
意見・経験・感情・価値観を切り分け、自分の判断を俯瞰することでメタ認知力を高められます。 |
|
日が落ちるのがすっかり早くなった。リフレクション(内省)には、この時間が最適ですね。 カフェに行ってラテを頼んで10分でも15分でも今日のことを整える。明日のことを考える。これでもかと整理されます。
落ち着いた眠りと明日のパフォーマンス爆上がり間違いなし。ぜひ今夜からどうぞ。 |
|
社員にリフレクション(内省)の機会を作るのは人事の仕事。
成長のサイクルは挑戦→成功・失敗→内省→改善→挑戦と続いていく、内省の有無で成長の質が大きく変わる。
業務の体験と内省の仕組みを整えるれば自走社員に成長させることができるのである。 |
|
今年読んだ本の中でも良書だと感じる1冊「リフレクション(自分とチームの成長を加速させる内省の技術)」が推せる。 自分はワークを通じて反省しすぎ、気を使いすぎて疲弊するタイプだと自己理解が捗って価値観のアンラーンができた。
経験からの学びを最大化するにはやはり質の高い振り返りが重要 |
|
【自分に問いかける時間】グループリフレクションの前に2週間を振り返る質問が書かれたリフレクションシートに記入します。
「2週間で何をやったっけ?」「なぜ私はそこに情熱を注いだんだろう?」記入するときから、リフレクション(内省)は始まっています。 |
|
一流は、ここぞという大事な場面ではつねに内省したうえで、アクションがとれる。
しかも、過去を振り返るために内省するのでなく、将来をより充実させるための内省は、学びと成長につながる。だから、内省(リフレクション)は「働く大人の学びと成長」と密接に関わる。 |
|
後悔するのはその都度、内省して先の行動を見直さなかったからだよ。多様な視点で行動を振り返ろうね。話のわかる人に話すことも内省に役立つよ。
失敗を糧にできるかどうかは内省(リフレクション)できるかどうかにかかっているのです。 |
|
リフレクションの目的は、経験からの学びを未来に活かすことです。リフレクションの前提には、
「成功しても、失敗しても、いずれにしても、経験したからこそ知っていることがある、経験を知恵に変えることができる」
という信念があります。 (リフレクション‐内省の技術 熊平美香) |
|
大学のとき、必修科目にリフレクション(内省)の授業があって受けたけれど、社会人になってからものすごく役立っている。
ふりかえりは何事においても大事なのに、方法は意外とわからない |
|
経営理念の実践発表会で最優秀に選ばれました。 自立主義から自律主義への内省、それを理念に絡めた実践というのが内容。 リフレクションのおかげです。 自分を理解するって大事。 |
|
マネジメントをどのように学んでいくか。
理学療法の世界においては、内省部分において適切なリフレクションを行う場が少ないのが現状ではないか。 |
|
内省出来るようになりたいのなら割と真面目にリフレクションがおすすめです。 慣れれば1人でも出来るし、臨床技術の向上も期待できます。
看護師教育では随分前からリフレクションを利用することが勧められていますし、リハ専門職の実習指導者講習会でもリフレクションが推奨されています |
|
みんな、ふりかえり、内省、リフレクションの目的を勘違いしてると思うんやけど。
何かをうまくいかせるとか成果残すため、じゃないんだよ。自分を理解するためです。
自分がどういう認知や意識、パターン、癖でどういうことを起こしているのか、ということを理解するため。 |
|
『直指人心(じきしにんしん)』
禅の四聖句シリーズ② |
|
転職活動では『セルフアウェアネス(自己認識)』を変化させ、高めていくことが必要だそう。
そのとき常に問われるのは「自分の中心にもっている軸やストーリー」だけど、最初から最後まで一貫している必要はなくて、変化していくものだと思う。 |
|
”反対意見に遭遇したら、相手はあなたの意見に反対しているのではなく、「自分が大切にしている価値観を、守ろうとしているだけ」”
お互いに納得のいく話し合いは、相手と自分の価値観を知ることから始まる。 |
|
成長の鍵は直接経験 人の成長を決める要素の割合の内 「直接経験」が70%!
つまり、経験から学びを得ることができる人が成長できる人だと思います。
経験を学びに変えるために、 『リフレクション(内省)』 が大切になります |
|
>経験が1番の先生〜 その言葉に共感します。 私はデービッド・コルブ提唱の『経験学習モデル』を活用しているので、経験、体験から成長するプロセスの有効性を知ってる
ポイントは内省(リフレクション)の気づきの深さと明確さだと思っていて、私はそこで問いかけと対話で支援してる |
・・・第二領域コーチングプログラムでは、この内省(リフレクション)の時間を強制的に確保していきます。
内省することで、第二領域のタスクが何かを極めたり、今のままで良いのかをチェックしていく部分もあるわけですが、
まさに、この内省自体が「第二領域のタスク」でもあるわけですね。
|
内省で人生が変わった13人の物語(ショートショート) |
先ほどは、納得のいく人生を送る上で、誰もが必ず一定の頻度でやらなければならない
「内省(リフレクション)」
について、その概要の解説と、Xの25人分の体験談をご紹介しました。
ただ、前回の体験談は、体験から得られた見解なども含めている場合もあり、少し抽象度が高い部分もありました。(Xは文字数も限られていますし)
そこで今回は、よりリアルな具体的なケースをもとに、
「どのようにして内省(リフレクション)によって人生が良くなっていくか」
をご紹介したいと思います。
内容は、私自身の体験や、私の身近な人・友人知人、メンバーさん(過去のプログラム含む)や読者さんからの話など、
私と皆さんの体験をベースに、アレンジ・創作を加えた小説ぽい形式にしました。なので完全な実体験そのものではなくフィクションですが、
【 内省(リフレクション)をすると、どのようにして人生や日々の改善・充実度アップ・成長につながっていくか 】
がリアルにわかるようになっています。
今回確認していただきたいのは、
「どういう流れで内省によって人生が変わっていくか」
「成長していくか」「問題が解決していくか」
といった点です。
体験ベースですが、あくまで参考事例ぽいフィクションの物語としてご紹介します。
内省(リフレクション)によって、どういう感じで人生が良くなっていくのか、問題が解決していくのかがピンとこない方は、ぜひ読んでみてください。
自分で言うのもなんですが、ショートショートみたいでそこそこ面白いのではないかと思います。
(すべて伝聞風にしていますが、私の体験談ベースのものもあります笑)
ケースは様々で、社会人の職場の人間関係、タスク管理、転職活動、大学生、人間関係、睡眠、食事などなど、あらゆるタイプがありますので、
おそらくご自身が心当たりのある話もあるかと思います。
前編と後編に分けてお届けします。まず前編は、比較的ディープな内面の課題や価値観などを中心にしました。
(その下の後編は集中力・食事・睡眠などのライフハック的な感じです)
内省によって人生がどう変わるのか。13人の体験談、ではどーぞ。
|
ToDoリストが埋まらないのは、“失敗するくらいならやらない方がマシ”という思い込み |
|
ある社会人が、
「今日はタスクをいくつも立てたのに、結局何も進められなかった」
という日が続いていました。
単に怠けていると思っていたのですが、内省してみると、
・本当は「やると決めたのにできなかった自分」になるのが怖かった
・「タスクをやらない=失敗していないという安心感」に無意識で逃げていた
ということに気づきました。
この恐怖心に気づいたことで、「完璧にやるより、一歩だけでも動く」ことに意味を感じるようになり、
ToDoリストも「成果ではなく動いた事実を記録するリスト」に変えたところ、前向きに取り組めるようになったそうです。 |
|
いいねが少なかった投稿が、自分の価値を揺らがせた |
|
あるフリーランスの人が、数日かけて考えた内容をSNSに投稿しました。
「これはきっと反応があるだろう」
と思っていたのに、結果は「いいね1件」だけ。 その瞬間、頭の中で次のような思いが駆け巡りました。
「自分には発信する価値がないのかもしれない」
その夜、モヤモヤした気持ちを内省ノートに書き出してみたところ、実は「いいね」の数そのものよりも、
「それによって“自分の価値が決まる”と思い込んでいた」
ことに気づきました。 思い返すと、自分がSNSをやっていた本当の目的は「共感を得ること」ではなく、
「学びや経験を誰かの役に立てたい」
という内面的な動機だったのです。それ以降は、
「反応を成果と見なさない」
などの工夫を取り入れ、数字に一喜一憂せず、自分の声を信じて発信できるようになったとのことです。 |
|
誰の役にも立てていない気がして、虚しさを感じた日 |
|
ある在宅ワーカーが、特に人と関わることもないまま1日が終わり、ふと
「今日、自分は何の役に立ったんだろう…」
と虚しさを感じました。
「何もしていないわけじゃないのに、なぜこんなに空しいのか?」
と自問し、内省してみたところ、心の奥にこんな思い込みがあると気づきました。
・「誰かの役に立っていない自分には価値がない」という前提が心の中にあった
・子どもの頃から、「役に立つ」「評価される」ことで褒められてきた
・「ただ存在しているだけでは価値がない」と信じていた自分がいた
この気づきを通じて、「誰かに必要とされること」と「自分自身を大切にすること」は別問題であると整理でき、
「今日やった小さなこと」
も、自分にとって価値があると少しずつ感じられるようになりました。
結果として、「貢献しなければ存在価値がない」という思い込みから少し距離を置くことができ、 他人の評価に振り回されず、日々の活動を自分の基準で捉える力がついてきたそうです。 |
|
週間目標の未達で気づいた、“理想を優先しすぎる癖” |
|
ある社会人が、「今週は毎朝6時起きで勉強をする」と目標を立てたものの、結局1日も実行できませんでした。
その週末、内省ノートに「なぜできなかったのか?」を書き出してみたところ、
・“こうあるべき”という理想を優先して、今の自分の生活リズムを無視していた
・できなかった自分を責めすぎて、次の目標を立てる気力までなくしていた
ことに気づきました。
それ以降、「現実の自分に合わせて調整する目標」を意識するようになり、 “習慣化を積み上げるスタイル”に切り替えたことで、結果的に継続率も達成感も向上しました。 |
|
自分に合った休み方の見つけ方“静かに座る”が苦手だった自分 |
|
ある人が、「休日に何もせずゆっくり過ごす」と決めていたのに、ソファで10分もすると逆にイライラしてスマホを触ってしまう…という状態が続いていました。
「なぜ、自分は“じっと休む”ことができないんだろう?」
と疑問に思い、数日間の記録と感情メモをもとに内省したところ、
・“動いていると気がまぎれる”性格で、「止まる=不安になる」傾向があった
・じっと休むのではなく、「気持ちが整う“動く休憩”」のほうが合っている
と気づきました。それ以降は、「コーヒーを淹れて、ゆっくり歩く」「観葉植物の手入れをする」「音楽をかけて片づけ」など、
“リラックスしながら、軽く動く”タイプの休憩を取り入れることで、心身ともにリフレッシュできるようになりました。 |
|
「休む=悪いこと」と思っていた自分に気づいた |
|
ある30代の在宅ワーカーが、「今日は休日」と決めていたにもかかわらず、 結局ノートPCを開いたり、タスク整理を始めてしまい、全く心が休まらないまま一日が終わってしまいました。
「自分は休むのが下手だな」と思いつつ、なぜ休めないのかをじっくり内省してみたところ、
“何かしていないと、価値がない気がする”という思い込み
「サボっている」「怠けている」と思われることへの強い恐怖
子どもの頃に「休んでばかりいるな」と言われた経験の記憶が残っていた
この気づきを通じて、「休むことも、生産性の一部だ」と定義を自分の中で書き換え、 スケジュール帳に「予定としての休憩時間」を明確に書くようにしたところ、ようやく気持ちが落ち着いて休めるようになったそうです。 |
|
職場の苦手な人を避けていたのは、“自分が否定される恐怖”からだった |
|
ある職場で、いつも何かと突っかかってくる年上の同僚が苦手で、できるだけ会話を避けていた社会人。
「性格が合わないから仕方ない」
と思っていましたが、ある日フィードバックの機会をもらったとき、その同僚が意外にも自分のことをよく見ていて、真剣にアドバイスしてくれていることに気づきました。
そこで改めて内省してみたところ、
「その人の前で自分の未熟さを見せたくない」 「正面から向き合うと傷つきそうで怖い」
という“否定されることへの恐れ”が根底にあったと分かりました。
その後は、相手の厳しさを「攻撃」ではなく「不器用な期待」と受け取れるようになり、 適度な距離を保ちつつも、業務上ではしっかり協力できる関係に変化したそうです。 |
|
なかなか応募できなかったのは、“否定されるのが怖い”からだった |
|
ある30代の会社員が、転職したいという思いはあるのに、求人を見ては閉じる…を何日も繰り返していました。
「まだ準備が足りないから」
と自分に言い訳していましたが、内省してその行動を振り返ってみると、
・書類を出して落ちたら、自分の経歴や価値が“否定された”気がしてしまいそうだった
・「どうしても行きたい」と思う会社ほど、怖くて応募できなかった
という本音に気づきました。
その気づきから、「評価されること」より「まず行動して、自分の市場価値を知ること」を優先するように切り替え、
最初の一通を出したことが転職活動のブレイクスルーになりました。 |
|
模試の点数を見たくなかったのは、夢を諦めることが怖かったから |
|
模試の成績表をなかなか開けずにいた受験生が、
「なぜ自分はこんなに模試の成績を見るのを避けているのか?」
と自問自答して内省してみたところ、
・「この点数ではもう無理だ」と言われるのが怖い
・成績を見ることで、「自分の夢に現実的な限界がある」と感じてしまうのが嫌だった
という気持ちに気づきました。
その後、「今の点数は“可能性の否定”ではなく“戦略の材料”だ」と捉え直し、点数を感情ではなく“情報”として扱う習慣がついたことで、前向きに勉強計画を立てられるようになりました。 |
|
飲み会に行かなかったのは、“場に馴染めない自分が怖かったから” |
|
ある会社員が、「疲れているし、行っても楽しくないから」と飲み会を断ったものの、 実はその飲み会でチームの新プロジェクトの話が盛り上がり、自分だけ蚊帳の外になってしまったことがありました。
後悔の気持ちを抱えながら内省してみると、
・「うまく話せず、場に馴染めなかったらどうしよう」
・「その場で浮くくらいなら、最初から行かない方がいい」
という“拒絶されることへの恐怖”が判断の背景にあったと気づきました。
それ以降は、「行く/行かない」の二択ではなく、「1時間だけ顔を出す」「後日1対1で会話する」など、“安心して関わるための選択肢”を持つようにしたそうです。 |
|
苦手な人を避けていたのは、“自分の否定を突きつけられる気がしたから” |
|
職場に、どうしても苦手な上司がいるという人が、内省を通して気づいたのは、
その人の価値観や仕事のやり方が「正論」であるだけに、自分が否定されているように感じていたということでした。
「自分はまだ不十分だ」と思っている部分を、あからさまに突かれる気がしてしまい、逃げるように距離を取っていた。
でも、内省してその感覚を見つめ直したことで、
「相手の存在が、自分の中の“未消化の課題”を映し出していた」
と気づけたそうです。以降は、その上司の言動に過剰反応しなくなり、苦手意識もうすれていきました。 |
|
人間関係で限界を感じたが、“自分の態度も冷たくなっていた”と気づいた |
|
ある在宅ワーカーが、上司の反応がそっけなくなってきたと感じ、
「自分は嫌われたのかもしれない」
と悩んでいました。 仕事はこなしていたけれど、内省してみると、最近の自分のチャットもかなり事務的だったと気づきました。
・「お疲れ様です。今週分の報告です」だけ送っていた
・以前より、報告頻度が減っていた
・相手の様子を気にかける言葉がなくなっていた
つまり、自分もまた“関係性の温度”を下げる一因になっていたと気づいたのです。
そこで次のメッセージでは、進捗の前に一言「最近バタバタしていて、でも元気です!」と添えたところ、 上司からも「わかる、自分も今週ぐったりしてた笑」と返ってきて、 「誤解だった」と安心できたそうです。 |
|
自分には強みがないと思っていたが、“人の話を受け止める力”に気づいた |
|
「自分には特にこれといった強みがない」と落ち込んでいたある社会人が、 後輩に「〇〇さんって、話しやすいですよね」と言われたことをきっかけに内省してみました。すると、
・相手の話を最後まで遮らずに聞く
・自分がしゃべるより誰の話でも聴くのが基本的に楽しい
・「なるほど、そう感じたんですね」と受け止める癖がある
といった自分の無意識のスタイルが、安心感を与えていたと気づきました。
それをきっかけに、「目立たないけど、場を落ち着かせる力」が自分の強みだと自覚するようになり、 チーム内でのファシリテーション(サポート役)や面談などを前向きに引き受けられるようになったそうです。 |
内省によって人生が変わることをイメージしていただけたでしょうか。
上記の事例は全て
「内省をしていなかったら、何も変わらなかった」
ものばかりです。インプットや経験をするだけでなく、内省と言うプロセスを踏むのがいかに大事か伝わったら幸いです。
|
内省の効果が凄かった10人のプチ体験談(後編) |
先ほどは比較的ディープな内面の課題も多かったですが、今回はライフハック系の内省の事例を中心にお届けします。
10人分のプチ内省物語です。では、どーぞ。
|
隙間時間をうまく使えなかったのは、“まとまった時間じゃないと意味がない”と思い込んでいたから |
|
ある受験生が、「1日の中で5分や10分の空き時間があるのに、うまく使えない」と悩んでいました。
隙間時間ができても「今やっても中途半端で終わるし…」とスマホを見て過ごしてしまうことが続いていたのです。
そこで内省してみたところ、
・“勉強は最低でも30分以上やらないと効果がない”という思い込みがあった
・短時間だと「やった気がしない」ので、無意識にやる気が削がれていた
という自分の「意味づけのクセ」に気づきました。
それ以降、「5分で1問だけ解く」「10分で復習カードを見る」といったミニタスクをあらかじめ用意し、
隙間時間があったら事前に決めた隙間時間用の勉強をするようになったところ、1日の密度が大きく高まったとのことです。 |
|
食事がただの作業になっていたのは、“効率ばかりを優先していた”からだった |
|
ある在宅ワーカーさんが、昼食を毎日10分で済ませることに慣れていました。
「サッと食べて、すぐ仕事に戻るのが効率的」と思っていたのです。
でもある日、昼食後も集中できず、ずっと疲れが取れない感覚がありました。
その違和感を内省してみたところ、
・食べる時間も「生産性の一部」としか見ておらず効率性を重視しすぎていた
・“休む”という目的を、完全に忘れていた
という、自分の思考の偏りに気づきました。
それ以降は、「一口ごとに味わう」「ゆっくりよく噛んで食べる」など、 食事そのものに意識を向ける習慣を取り入れたことで、午後の集中力も自然と戻るようになったそうです。 |
|
未完了のタスクだらけの日が、自分の優先順位を見直すきっかけに |
|
ある日、ToDoリストのタスクが半分以上終わらずに1日が終わった社会人が、落ち込んで、振り返りと共にいつもより深い内省をしてみました。
その中で気づいたのは、
・本当に重要なタスクではなく、「すぐ終わること」や「人に頼まれたこと」を優先していた
・自分にとって意味のある仕事を後回しにしていた
という現実でした。
この内省を通じて、「ToDoリストは“消化するもの”ではなく“人生の設計図”」という意識が芽生え、 翌日からは「1日の最初に“本当にやるべき1つ”を書いてから他のタスクを書く」習慣に変更しました。
この変更により優先順位の基準もできて、生産性・充実感が大きく変わったそうです。 |
|
寝る前にスマホを見続けた夜が、人生の習慣設計を変えた |
|
ある社会人が、就寝前にスマホを1時間以上見てしまい、翌朝体調がすぐれませんでした。
「やっちゃったな…」と思いながら、なぜ寝る直前にスマホを手放せなかったのかを書き出してみたところ、
・仕事が終わった実感を得られず、ダラダラと「自分の時間」を求めていた
・本当は、スマホではなく「リラックスや癒し」が必要だった
と気づきました。
それ以来、寝る前に「お風呂→読書→間接照明だけの部屋で横になる」という新しいルーティンを試したところ、
自然と眠れるようになり、翌日の集中力にも良い影響が出るようになりました。 |
|
読書に意味を感じられなかったのは、“すぐ成果につながらないとダメ”と思い込んでいたから |
|
ある20代の社会人が、読書を習慣にしたいと思っても、毎回3日坊主で終わっていました。
「読んでもどうせ忘れるし、仕事に直結しないし…」
と、だんだん遠ざかっていったそうです。
でもある日、たまたま読んだ本の一節が心に引っかかり、それをきっかけに自分の考え方が少しずつ変わっていくのを感じました。そこで内省してみたところ、
・“読書は、即効性のある知識を得るためのもの”という思い込みがあった
・“すぐ役立たない=無意味”と切り捨てていた
という、自分の中の「成果至上主義」に気づきました。
それ以降は、「今すぐ役立たなくても、自分の思考の栄養になる」と考えるようになり、 気楽に、でも継続的に読書と付き合えるようになったとのことです。 |
|
何気ない親の一言が、見方を180度変えた |
|
ある社会人が実家に帰省した際、親から「最近あんた全然連絡くれへんな」と何気なく言われ、
その時は「忙しいのに何も分かってないな」とモヤっとした気持ちになりました。
しかし帰宅後、ふとその場面を思い返して内省したところ、
・「構ってほしい」のではなく、「無事に過ごしてるかを知りたい」だけだったこと
・自分も「心配されるのが面倒」だと思って距離を取っていたこと
に気づきました。
それからは、週1回の短いLINEや電話を習慣にすることで、家族との関係がグッと良くなり、かえって自分の気持ちも安定するようになったとのことです。 |
|
夜にどか食いしてしまった理由を深掘りしたら、意外な本音が出てきた |
|
ある日の深夜、急にポテチやアイスをドカ食いしてしまい、あとから自己嫌悪になった人が、 なぜこんなことをしたのか?とノートに書き出して内省してみたところ、
・「今日は何も達成できなかった」という虚無感
・「1日をこのまま終えたくない」という抵抗感
・「“自分にごほうび”をあげたかった」という甘え
という複雑な感情が交じっていたと気づきました。
それ以降、夜に「今日の満足ポイントを3つ書いてから寝る」習慣をつけたことで、 |
|
軽い散歩が、集中力を取り戻す“切り替えスイッチ”だった |
|
ある社会人が、仕事中にどうしても集中できず、「気分転換に10分だけ」と外を歩いてみました。
すると、その後の作業が驚くほどスムーズに進みました。そこでその夜、
「なぜあれだけで変わったんだろう?」
と内省してみたところ、
・視界が開けて、脳のモードが切り替わった
・歩くことで、体の緊張がゆるみ、思考も流れ始めた
ということに気づきました。
それからは、頭が重たいときほど「意識的に動く」ことを意識し、10分の散歩を「思考を切り替えるトリガー」として活用するようになったそうです。 |
|
同僚の一言にモヤモヤしたのは、“自分が嫌われたと思い込んでいたから |
|
ある会社員が、同僚に軽くツッコミを入れられた場面で、なぜかずっとその言葉が気になっていました。
「なんであんなふうに言われたんだろう…」と。そこで内省してみると、
・相手の言葉よりも、「自分は嫌われてるのでは?」という不安の方が先にあった
・これまでも、人の機嫌に敏感すぎる自分がいた
という自分の“過剰な読み取り癖”に気づきました。
その後は、「相手の表情や言葉に反応する前に、自分の感情を一度チェックする」習慣を取り入れ、必要以上に人間関係で疲れることが減ったとのことです。 |
|
家事がめんどうだと思っていたけれど、“気分転換になるスイッチ”だったと気づいた |
|
ある在宅ワーカーが、仕事の合間にやるはずだった家事を、何日も後回しにしていました。
「忙しいときに、なんでこんなことまで…」とイライラしていたそうです。
でもある日、行き詰まった作業の手を止めて、仕方なくキッチンの洗い物をしたところ、終わったあと、なぜか頭の中がスッキリしていることに気づきました。
その後、部屋の掃除や洗濯などの家事の後も、同じような感覚になることがわかりました。 そこで内省してみたところ、
・手を動かす単純作業が、考えごとから一旦意識をそらしてくれていた
・家事は仕事と種類が全く違うので、気分転換になって仕事のストレスが減っていた
ということに気づきました。
それ以降は、「やらなきゃ」ではなく「ちょっと気分転換しよう」のつもりで、洗濯・掃除・食器洗いを取り入れるようになり、集中力の回復にも役立つ大事な習慣になったそうです。 |
|
内省の5人(謎の疲労感,SNS,恋愛,残業,転職)+メンバー5人の感想 |
今回も、内省(リフレクション)によって人生が変わったプチ物語(5人分)をお届けします。
ついでに、第3期より内省の時間を導入したので、それに対する継続メンバーさんの感想(5人分)も、その後に追加しておきます。
今回のプチ物語の5人のテーマは、
【 謎の疲労感、SNSの情報発信、大学生の恋愛、残業、転職 】
となっております。どの事例も共通するのは、
「内省をしていなかったら、何も変わらなかった」
ものばかりです。
大量にインプットや経験をするだけでなく、内省のプロセスを踏むのがいかに大事か伝わったら幸いです。
(以下、内省のプチ物語5人のあと、プログラムのメンバーさんの内省についての感想5人分も掲載)
|
謎のだるさと浅い眠りの原因は、意外と単純なことだった |
|
ある40代の会社員が、ここ最近ずっと体がだるく、夜も眠りが浅くて朝にスッキリ起きられない日が続いていました。
「年齢のせいかもしれない」
と思いながらも、何となく不調の原因が気になり、内省ノートに最近の生活を振り返ってみました。すると、
・ここ2週間、ずっとシャワーだけで済ませていて湯船に浸かっていなかったこと
・入浴をやめたのと同じ時期から、体調の違和感が始まっていたこと
に気づきました。
そこで久しぶりに湯船にゆっくりと浸かってみたところ、その翌朝、体が軽く感じられ、久々にぐっすり眠れた感覚があったそうです。
「こんなに違うんだ…」
という驚きとともに、“疲れを取るために必要な習慣”を無意識に省いていたことを反省し、 それ以降、入浴を大事なメンテナンスの時間として捉え直すようになったとのことです。 |
|
「もっといい人がいるかも」と思ったのは、“飽きっぽい自分の癖”に気づけていなかったから |
|
ある女子大生が、3年付き合っている彼氏と一緒にいても、以前のようにドキドキしなくなっていることに気づきました。
最近では、「もっと自分に合う人が他にいるんじゃないか?」という考えが頭をよぎることも増えていました。
一度その気持ちを整理しようと、内省のノートに今の気持ちを書き出してみたところ、
・関係がマンネリ化してきただけで、彼氏に問題があるわけではない
・むしろ、彼は自分を本気で大切にしてくれていて、人間的にも信頼できる存在だった
という事実に改めて気づきました。さらに振り返ると、自分は過去にも、習い事やバイト、人間関係などで
「新鮮さがなくなると飽きてしまう」
傾向があったことを思い出しました。そのうえで、「恋愛において本当に大事なのは、“ときめき”より“関係の質”なのかもしれない」と考えるようになり、
パートナーとの関係も、感情の波ではなく、信頼と継続の積み重ねで育てていきたいと思うようになったそうです。 |
|
Xで伸びなかった理由は、“自分の強みを思い出せていなかった”からだった |
|
ある会社員の女性が、副業のためにXでの情報発信を続けていました。
毎日投稿をしていたものの、反応は少なく、フォロワーもほとんど増えない状態が数ヶ月続いていました。
「自分には向いてないのかも…」
と落ち込んでいたとき、なぜここまでやってきたのか、自分に何ができるのかを内省してみました。 その中でふと思い出したのは、
・過去にプレゼンやスピーチで「わかりやすかった」と何度も言われたこと
・話すことで人に伝えるほうが、ずっと楽に感じていたこと
という、自分の“伝え方のスタイル”でした。
「〇〇ちゃんと話していると元気が出るよ」とこれまでよく言われていたことも思い出しました。
そこから思い切って、短い動画での配信に切り替えてみたところ、フォロワーの増加や反応の伸びがすぐに現れ、「ちゃんと伝わってる!」という実感を持てるようになったそうです。
今では「文章で勝負しないといけない」という思い込みも手放し、“自分らしい伝え方”に自信を持って取り組めるようになったとのことです。 |
|
残業が当たり前になっていたのは、“周りの目”と“ゆるんだ時間感覚”に気づいていなかったから |
|
ある30代の会社員が、気づけば毎日残業しており、家に帰っても疲れ果てて何もできない日々が続いていました。
「仕事が多いから仕方ない」と思い込んでいたものの、ある夜ふと、
「なぜ自分はこんなに働いているんだろう?」
と自問し、内省をしてみました。すると、
・みんなが残っているのに自分だけ先に帰るのは、悪いことのように感じていた
・“どうせ残業するから”という気持ちで、日中の仕事も無意識にゆるんでいた
という、自分の思い込みと行動パターンに気づきました。
そこで週に2日だけ「ノー残業デー」を設定し、思い切って同僚にも
「仕事の効率を高めるために、試しにこの曜日は必ず定時で帰ります」
と宣言してみました。幸い、生産性アップの工夫を推奨する社風なのでみんな受け入れてくれました。すると不思議なことに、
「終了時刻を必ず守る!」
という意識が強く働き、日中の仕事の集中力が格段に上がり、実際にノー残業デーは達成、他の日の残業も大幅に減りました。
さらに、それを見た周囲の同僚も「ノー残業デー」を真似する人が増えていきました。
今では「残業すること」ではなく、「限られた時間で効率的に集中して働く」という強い意識で成果は変えられると、実感するようになったそうです。 |
|
転職を迷っていた理由は、“本当に大事にしていること”を見失っていたから |
|
ある社会人が、
「今の仕事、このままでいいのかな…」
と転職を考えていました。
仕事内容に飽きてきたことや、他の会社のほうが条件が良さそうに見えたこともあり、求人サイトを眺める時間が増えていました。
でもいざ応募しようとすると、なぜか気が進まず、モヤモヤとした状態が続いていたのです。そこで一度立ち止まり、
「自分にとって、仕事で大事にしていることは何だろう?」
と内省してみたところ、
・やりがいよりも、“誰と働くか”を大事にしている自分に気づいた
・今の職場には、尊敬できる上司や、気を許せる同僚がいる
・それが、思っていた以上に自分にとっての支えになっていて1番重要な価値観
ということが分かりました。
その気づきを得てからは、「環境を変えること」よりも、
「今の場所で、どんなふうに関わっていくか」
を考えるようになり、転職の選択肢はいったん脇に置くことにしたそうです。 |
以下は、プログラムを継続するメンバーさんから最近届いた、第3期から内省の仕組みを導入することについての感想です。参考までに掲載しておきます。
|
内省というのは自分の中でも大切にしたいテーマでした。
自分を振り返り、気づき、今後に活かす。 その様なことをコーチングで行って頂けることに感動したため。
切磋琢磨でき、新しい気づきや学びを頂けるナイスな場であるため。
波のある日常の中で、忙しい時期でも少しでも第二領域に取り組めることが、想像以上に精神的な安定に繋がり、元気を貰っている様に思います。
また、共にそれぞれの環境の中で自らの第二領域に取り組んでいる仲間がいて、 その様子を見たり、感じたりすることも、自分を癒し、元気づけてくれている様に思います。とても有り難く、大感謝です。
日常の波に揉まれながらも、第二領域に取り組むことができているのは、この場があるお陰です。
ずっとシステム的に取り組みたいと思っていた内省の時間まで取り入れて頂き、感激です。 今年度も何卒よろしくお願い致します。 |
|
週間目標を立て、報告する事により第2領域がどんどん進む事を実感したため、今後も続けて行きたいと思いました。
内省を強制的にできる環境に魅力を感じました。
毎日振り返りはしているが、そこまで深くはしていない&できていないので、もう少し掘り下げる事によってどうなるか試してみたいと思いました
他にも作業ルームや起床就寝報告などを使用したいです |
|
コーチングプログラムに参加してから、計画を立てそれを振り返るという作業を初めてまともにやってみて時間に追われるのではなく時間をコントロールする感覚を味わうことができました。
やりたいやりたいと思いながら忙しさにかまけて放置していたことにも取り組めました。道は遠いですけど最初の一歩を踏み出せたのは大きかったです。
このプログラムに内省の時間が強制的に設けられると知った時は正直負担に思ったのですが、
「今までもそれを繰り返してきたからよくなっていったんだ」
と思い、大きく自分を覗き込む時間を作れることが楽しみになってきました。
故に継続して人生をよりよいものにしていきたいと思います。 |
|
セッション時間の活用方法については自分自身、ちょっとモヤモヤしてました(せっかくの時間なのにタスク消化に終わるのがもったいないと思っていたけど改善できていなかった)ので、
今回「内省」という新しい考え方?仕組み?が入ったのは良さそうに感じました。
もともと週の振り返りに時間をかけて自問自答するタイプなので(ストリングスファインダーでも自分の強みTOP5のうち「内省」が2位)、今回の仕組み変更は自分に合いそうな気がします。
1年間で自分にどんな変化が訪れるのか、楽しみながらやっていきたいと思います。
また1年、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 |
|
内省の作業をぜひやりたいと思いました。
最近、週間目標もとりあえず続きをやろう…と惰性っぽくなっていることに気づいていましたが、改善することもできず…。〇〇〇〇(※ご本人のタスク)をただ続けることにも疑問を持っていました。何のためにやってるのか分からなくなっていました。
強制される時間がないとなかなか自分とじっくり向き合うことは難しいと感じています。
最近始めた〇〇〇〇〇(※内省に似た部分があるライフハック)よりももっと深く考える感じかなと感じて大変興味深いと思っています。
できるかどうかわかりませんが、強制的な(?!)内省の時間が楽しみです。
また1年間、よく考えて第2領域に取り組んでいきたいです。 |
|
本プログラムにおける内省のやり方 |
本ページは、内省の解説・やり方・具体例・体験談をお伝えする専用のページです。
私(中西)が運営する「第二領域コーチング・プログラム」では、私が開発した独自の内省法を元に内省を実施しています。
2023年の第1期、2024年の第2期と、第二領域(緊急ではないけど重要)のタスクを実行する点にフォーカスしてきましたが、
2025年の第3期からは「内省の重要性」と「内省は第二領域の筆頭」である点をふまえ、プログラム内で強制的に内省を実施できる仕組みを導入しました。
上記で一部紹介した感想にもある通り、すでにメンバーの皆さんから大好評です(特に私が考案した独自の内省法は、ゲーム的に非常に楽しく内省ができるようになります)。
詳細ついては本プログラムのこちらの案内ページをご覧ください。